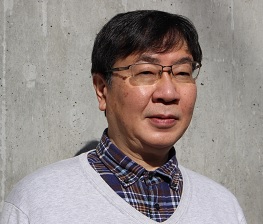
 石破首相が10月10日、「内閣総理大臣所感――戦後80年に寄せて」と題する文書を発表し、記者会見を行いました。この「所感」をまとめるにあたって首相は多くの研究書を渉猟し、北岡伸一・東大名誉教授など斯界の権威の意見を聞き、自身も20回ほど推敲を重ねるなど、並々ならぬ情熱を傾けた由です。
石破首相が10月10日、「内閣総理大臣所感――戦後80年に寄せて」と題する文書を発表し、記者会見を行いました。この「所感」をまとめるにあたって首相は多くの研究書を渉猟し、北岡伸一・東大名誉教授など斯界の権威の意見を聞き、自身も20回ほど推敲を重ねるなど、並々ならぬ情熱を傾けた由です。
しかしご本人にとってはアンラッキーなことだったかと思われますが、公明党が連立政権から離脱するというニュースが直前に飛び込み、世上の関心はすっかりそちらに奪われてしまった感じです。テレビ報道も公明の連立離脱ばかりとなり、翌日の新聞も第一面トップはそのニュースが占めて、石破首相の「所感」は脇に押しやられてしまいました。それでもこの「所感」は意義があったのでしょうか?
一国の総理大臣としての立場から出した文書ですから、その中身が大事なのはもちろんですが、それがどのような政策となり、現実の政治をどう動かすのかという観点から評価する必要があります。その意味では、この所感の意義を論じるのは時期尚早かもしれません。
とはいえ、わたしはその意義の評価に関して今一つ消極的です。第一に、石破氏の首相としての持ち時間があまりに少ないことです。せっかく建設的なよいことを述べても、間もなく首相を退任しなくてはなりません。ここで述べたことを政策化する猶予は全く残されていないのです。たとえば米国の大統領のように4年間の任期があれば、具体化してゆく手立てはあるのでしょうが、1年で交代では大したことはできません。
第二に、石破氏の後任がそれを引き継ぐということであれば、「所感」の中身を具体化することも可能でしょうが、高市総裁をはじめ、自民党保守派はそもそもこの「所感」自体に反対です。本来であれば、歴代首相が10年の節目ごとに発表してきた「首相談話」を石破氏も公表したかったのですが、政権内ではそうした談話は戦後70年の「安倍談話」を最後とし、もはや「反省」や「おわび」を内外に表明すべきでないとの意見が強く、結局、閣議決定を経た談話の発出は取りやめざるを得ませんでした。そこで石破氏は首相個人の「所感」という形で思いを述べるにとどまったわけですので、今後高市氏が新政権を発足した場合(公明党の連立離脱で、すんなり高市政権が成立するかどうかは微妙な情勢ですが)、この「石破所感」はないがしろにされる可能性大です。
 「所感」で述べられた内容についてはどう考えますか?
「所感」で述べられた内容についてはどう考えますか?
「所感」の内容と、記者会見における質疑応答は、「首相官邸」のホームページに載っていますので、それを見るのが一番です。
内容自体については、新聞を読むと賛否両論あります。「首相談話」を継承するのであれば、中国などアジア諸国への言及があって然るべきなのに、それが欠如している点を物足りなく思う意見、逆に、わが国が無謀な戦争を行ったことを石破氏は最大の問題としているが、日本があのような戦争へと追い詰められた当時の国際情勢を客観的に分析すべきではないかとの意見など、それぞれもっともな指摘ではあります。
しかし石破首相は歴史研究者として学会報告をしたのではありません。為政者として、論点をしぼって問題提起したのです。所感の最初の部分で述べられているところを引用してみます。「過去3度の談話においては、なぜあの戦争を避けることができなかったのかという点にはあまり触れられておりません。戦後70年談話においても、日本は『外交的、経済的な行き詰まりを、力の行使によって解決しようと試みました。国内の政治システムは、その歯止めたりえなかった』という一節がありますが、それ以上の詳細は論じられておりません。国内の政治システムは、なぜ歯止めたりえなかったのか。」
 で、それに対する石破首相の見解はいかなるものなのでしょう?
で、それに対する石破首相の見解はいかなるものなのでしょう?
その見解は決して突飛なものではなく、歴史を学んできた者からすれば、オーソドックスで穏当なものです。ただ、自民党という保守政党のトップの口から、政治学者の丸山眞男、天皇機関説の美濃部達吉、リベラル政治家の石橋湛山、反軍演説で有名な斎藤隆夫の名前が肯定的に発せられたことにわたしはいささか驚きました。これらの名前は従来、リベラルあるいは「左派」の人々が敬愛し口にしてきましたので。
それはともかく、石破氏が引き出した結論を大づかみに要約すれば、先の大戦では、政治が軍部を統制する「文民統制」が存在せず、軍部の独走を政治家たちが止めるシステムがなかったのが最大の問題だったというものです。議会も機能せず、テロに怯える政治家も軍に迎合し、メディアも勇ましさを賛美し戦争機運を煽ったといった実態が整理されて述べられました。正直なところ、このへんは少しでも真面目に歴史を学んできた者からすれば常識的な知識であって、学問的な見地からすれば新味はありません。しかし、繰り返しになりますが、石破氏は歴史の研究者ではなく現実に政治を動かす立場にある人です。あくまで今の政治に問題関心があるのは言うまでもありません。
 今の政治への問題関心とは具体的に何ですか?
今の政治への問題関心とは具体的に何ですか?
それは「所感」のなかの「今日への教訓」の章に抽象的な形で述べられています。たとえば「無責任なポピュリズムに屈しない、大勢に流されない政治家としての矜持と責任」、「状況が行き詰まる場合には、成功の可能性が低く、高リスクであっても、勇ましい声、大胆な解決策が受け入れられがち」、「政治は一時的な世論に迎合し、人気取り政策に動いて国益を損なうような党利党略と己の保身に走っては決してなりません」、「偏狭なナショナリズム、差別や排外主義を許してはなりません」等の言葉から自ずと浮かび上がってきます。
要するに石破氏は、このままだと日本がまた戦争への道を突き進みかねない、偏狭なナショナリズムやポピュリズムがそれを後押ししていると危機感を抱いているのでしょう。その点は、わたしも同感なのです。先日の参院選で示されたような外国人排斥の機運、「日本人ファースト」的風潮、中国との対決を歓迎し、その逆の立場を「媚中派」と呼び侮蔑する態度に、わたしも危機感を募らせています。
この流れを極右的な政治路線とすれば、高市新総裁を核として、そうしたレールが敷かれつつあるように見えます。それを止めるには、まさに解党的な政治刷新が必要です。公明党の連立離脱は、その実行と位置付けられるかもしれません。とすると、高市総裁の路線にノーを突き付けたと見なし得る石破氏の「所感」は、案外、公明党の動きと連動しているのかもしれません。首相を退任する石破氏に政治家としてさらに大きな働きを期待するのは買いかぶりでしょうか。
—————————————
河原地英武<京都産業大学国際関係学部教授>
東京外国語大学ロシア語学科卒。 同大学院修士課程修了。 専門分野はロシア政治、安全保障問題、国際関係論。 俳人協会会員でもある。 俳句誌「伊吹嶺」主宰。
