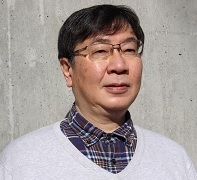
 9月25日にわが国政府の複数関係者が明らかにしたところによれば、10月末に米国のトランプ大統領が訪日し、日米首脳会談を行う方向で調整に入ったとのことです。
9月25日にわが国政府の複数関係者が明らかにしたところによれば、10月末に米国のトランプ大統領が訪日し、日米首脳会談を行う方向で調整に入ったとのことです。
それが実現するとして、準備期間はあと1ヵ月しかありません。しかも日本は新首相がだれになるかも未確定の状態ですが、なぜこのような慌ただしい状況下で首脳会談が行われるのでしょうか?
たしかにこのスケジュールでは日本側もあまり準備ができませんね。今年2月に石破首相が訪米した際には、トランプ大統領との会談対策として、事前に各省庁の担当者を首相官邸に呼んで、首相自らが30時間に及ぶ「勉強会」を行ったと報じられましたが、今回はそうした準備を行う余裕はないでしょう。まず10月4日に自民党総裁選の投開票が行われ、その結果を踏まえて10月中旬、臨時国会における首相指名選挙がなされ、ようやく首相が決まります。新首相は組閣に取り組まねばならず、10月いっぱいは落ち着いて政治をすることは難しいと思われます。日米首脳会談の準備も官僚主導で進めるほかないでしょう。
ただ、こうした日本側の事情は米国も先刻承知の上ですので、首脳同士の真摯なやり取りが行われることはないものと思われます。儀礼的な会談になることは致し方ありませんし、トランプ政権としては対策が不十分な日本に対し、いわば「先制パンチ」的に強い要求を出し、新政権の反応を探るといった策に出る可能性も否定できません。野党と連立を組まなくては成り立たない少数与党政権を相手に、米国が十分な敬意を示すことはないのではないかと危ぶみます。ともかく今回の首脳会談に関しては、トランプ大統領の都合が優先されたのだろうと推測します。
 トランプ大統領の都合とは?
トランプ大統領の都合とは?
周知のように10月31日と11月1日に韓国の慶州でアジア太平洋経済協力会議(APEC)が開催されます。それに出席するトランプ大統領は、10月26日~28日にマレーシアで開かれる東南アジア諸国連合(ASEAN)関連の首脳会談に出席することも検討しており、マレーシアから韓国へ行く途中に日本を訪れるという段取りを組んでいるようです(『朝日新聞』9月26日)。
 この秋はトランプ外交がアジアに焦点を当てていると言えば言いすぎでしょうか?
この秋はトランプ外交がアジアに焦点を当てていると言えば言いすぎでしょうか?
その見方は的を射ているかもしれません。今までトランプ政権はウクライナ戦争やガザ地区の紛争を終わらせようといろいろ策を講じてきましたが奏功しませんでした。イランとも交渉再開のめどは立っていません。アジア方面でもトランプ大統領の目覚ましい成果はまだありません。ところが中国はこの9月初頭、ロシアと北朝鮮の首脳を北京に集めて中露朝の結束を誇示するなど「強さ」を見せつけています。アジアで米国がこれ以上遅れをとることはできないとトランプ政権は考えているのではないでしょうか。そして、米国のアジア政策のなかで最も重視されているのは対中関係です。
 なぜそう言えるのですか?
なぜそう言えるのですか?
実はトランプ大統領のAPEC参加も、中国の習近平国家主席との会談が最重要事項と見なされているのです。もともとトランプ氏は、APECに合わせて北京を訪問し、米中首脳会談を行いたいとの意向を示していました。9月9日にはへグセス米国防長官が中国の菫軍国防相とビデオ会議を行い、翌10日にはルビオ国務長官が王毅外相と電話で会談しましたが、これらは北京での米中首脳会談の実現に向けての準備だったと考えられます(『讀賣新聞』9月11日)。
9月19日、トランプ大統領が習近平主席と電話で会談し、結局、トランプ氏の訪中は年明けとなることに決まりましたが、APECに合わせ、韓国でも対面で首脳会談をすることが約束されました。また、来年のトランプ大統領訪中後には、習近平氏も「適切な時期」に訪米することになったようです(『讀賣新聞』9月20日夕刊)。
 米国のバイデン前大統領は中国を「専制主義」と呼び、民主主義陣営の結束を唱え、対中敵視政策を推し進めました。またトランプ氏も一時は中国との「関税戦争」を繰り広げましたが、ここに来て米国の対中批判がトーンダウンしているように見受けられるのですがどうなのでしょう?
米国のバイデン前大統領は中国を「専制主義」と呼び、民主主義陣営の結束を唱え、対中敵視政策を推し進めました。またトランプ氏も一時は中国との「関税戦争」を繰り広げましたが、ここに来て米国の対中批判がトーンダウンしているように見受けられるのですがどうなのでしょう?
たしかにその通りです。『日経新聞』(9月10日)も「トランプ氏、対中敵視しぼむ 来月末に首脳会談案 覇権争い岐路」という見出しを掲げ、トランプ政権の変化を指摘しています。その内容をなぞる形で述べますと、トランプ氏は8月末、「厳しく制限している中国留学生を60万人も受け入れる可能性に触れ、習氏に秋風を」送りました。米国防省も、「中国の領土拡張は容認しないものの、現状維持が続く限り権威主義的な体制を批判しないとの考えを強調」しています。また、対中強硬派として知られるルビオ国務長官も最近では「中国への厳しいトーンを抑えている」とのことです。
米中関係の改善を象徴するのが中国発の動画共有アプリ「TikTok」の米国事業を米国側へ売却する問題でしょう。米中両政府は9月15日、スペインで開かれた閣僚級協議でTikTok売却に関して大枠の合意に達しました。9月19日の米中電話首脳会談でもこの問題が話し合われ、一定の進展があった模様です。↓
中国側がTikTokの米国事業を米国企業に売却することは、一見すると中国側の譲歩のように見えますが、双日総合研究所の吉崎達彦氏(チーフエコノミスト)は、むしろ「トランプ氏は中国にどんどん取り込まれている」と警鐘を鳴らしています。TikTokを米国側に売却しても、米国で動画の表示順を決めるアルゴリズム(計算順位)に中国の技術を使い続けることに変わりはないからだそうです。中国のアルゴリズムを使い続ければ、中国が米国の世論を都合のいいように動かす懸念は消えません。しかしトランプ氏自身が2024年の米大統領選でTikTokを活用して当選を果たしたこともあり、「敵に回せなくなった」からだというのです(「日経速報ニュースアーカイブ」2025/09/19 05:00)。
いずれにせよ米国は、従来の中国との対決姿勢から、平和共存への方向転換を模索しているように思われます。
 とすれば、「台湾有事」の可能性も遠のき、東アジアに平和がもたらされるわけで、日本としても南西諸島の防衛強化などに膨大な予算を割かなくてよくなるのでしょうか?
とすれば、「台湾有事」の可能性も遠のき、東アジアに平和がもたらされるわけで、日本としても南西諸島の防衛強化などに膨大な予算を割かなくてよくなるのでしょうか?
そこが難しいところです。トランプ政権は中国の軍事的プレゼンスが増大する台湾や南シナ海の情勢を、米国が責任を負うグローバルな課題から、周辺国が対処すべきローカルな課題へと「格下げ」する懸念があるのです。
トランプ氏は今年6月、欧州の問題はまずもって欧州が対処すべしとの立場からNATO諸国に防衛費のGDP比5%引上げを吞ませました。同様のことをアジア諸国に求める公算は大だと言わねばなりません。来月のトランプ大統領訪日時に、首脳会談でそのあたりが議題とされるかもしれません。こうした事情は韓国の場合も同じで、トランプ政権から韓国も防衛費増を求められています。そう考えると、米中関係が改善し、米軍のアジアにおけるプレゼンスが縮小された場合、安全保障面では、日本などの当事国の負担が逆に大きくなることになりかねません。
—————————————
