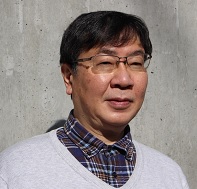
 広島に原爆が投下された8月6日、長崎に投下された8月9日には、メディアも大きく報じ、様々な特集を組むことは恒例になっていますが、今年は例年以上にメディアが力を入れて報道していたように思われます。またネットなどを見ても、世論の関心がいつになく高まっていたように感じますがいかがでしょう?
広島に原爆が投下された8月6日、長崎に投下された8月9日には、メディアも大きく報じ、様々な特集を組むことは恒例になっていますが、今年は例年以上にメディアが力を入れて報道していたように思われます。またネットなどを見ても、世論の関心がいつになく高まっていたように感じますがいかがでしょう?
同感です。先日、わたしが主宰を務める「伊吹嶺俳句会」の定例の句会に出かけてきましたが、「原爆の日」を詠んだ真摯な句がいくつも出され、驚きました。ちなみに原爆投下の日はちゃんと季語にもなっており、歳時記に載っています。8月6日は「原爆忌」「原爆の日」「広島忌」として「夏」の部に置かれ、8月9日は「原爆忌」「原爆の日」「長崎忌」として「秋」の部に入れられています(『合本 俳句歳時記 第四版』角川学芸出版)。
毎年、この時期に俳人が「原爆の日」の句を作るのは当然ですが、今年は句友の作品の緊迫感が一段と高まっているとの印象を受け驚いたのです。たとえば、我々は何をなすべきかを自問自答する句、黙祷の「六十秒間」の重みを詠んだ句、「八時十五分」を詠みこんだ句などが出されました。「八時十五分」は広島に原爆が投下された時刻です。言い添えれば、長崎に投下されたのは11時2分です。今まで、時刻まで記憶している人はあまりいなかったのではないでしょうか。しかし今年は、メディアの力も大きいと思われますが、少なからぬ国民が、原爆投下の日にちだけでなく、時刻まで記憶に刻むことになりました。
 それだけ多くの人が核兵器の問題に危機感を募らせていると見ていいのでしょうか?
それだけ多くの人が核兵器の問題に危機感を募らせていると見ていいのでしょうか?
そうかもしれません。その理由として、戦後80年という節目が一人一人の意識に大きな影を落としていることが大きいと思われます。被爆体験者、そして戦争体験者が非常に少なくなるなかで、戦時の悲惨な体験と侵略戦争の反省の上に立った戦後わが国の平和主義の存続が揺らいでいるのが現在です。
平和主義の一角を担うのが非核三原則ですが、石破首相は本来、米国との「核共有論」の推進派でした(米シンクタンク「ハドソン研究所」のHPに2024年9月27日掲載の石破論文「日本の外交政策の将来」参照)。しかしここに来て、石破氏は改めて非核三原則を堅持し核共有論を否定する旨明言し、従来の平和主義遵守の意向を示しました。↓
日本の平和主義は終戦記念日にあたって10年ごとに行われてきた歴代首相談話(1995年8月15日の村山首相談話、2005年8月15日の小泉首相談話、2015年8月14日の安倍首相談話)によって確認されていますが、石破首相が今年、これを踏襲した談話を発するか否かが注目を集めているところです。
 他方で、わが国が核兵器を保有することを肯定的にとらえる声が大きくなりつつあるのも確かなのではありませんか?
他方で、わが国が核兵器を保有することを肯定的にとらえる声が大きくなりつつあるのも確かなのではありませんか?
世論がその方向に傾きつつあるとまでは言いませんが、声の大きな人たち(政治家やオピニオンリーダー)の影響力は無視できなくなってきました。先の参院選で参政党から立候補して当選したさや氏(現在、本名の塩入清香で活動)が、選挙期間中、あるネット番組で「核武装が最も安上がり」だと発言したことが大きな反響を呼びました。批判も続出しましたが、今回大躍進をとげた参政党の支持者は、この発言を承知のうえで一票を投じたという事実は重く受け止めるべきです。
京都の西田昌司議員が、「ひめゆり発言」で大批判を浴びながら、結局、参院選で当選した事実も見過ごせません。彼は「自虐史観」からの脱却を持論とし、故安倍晋三氏の同志でしたから「核共有論」の推進派です。京都府民が彼を選んだということは、その立場を肯定したことを意味します。
わたしにもある体験があります。コロナ禍以前のことになりますが、関西某市の市役所企画課が後援している時事問題に関する市民講座(毎月1回開催)の講師を頼まれました。前任の先生がご高齢で降板されたので、その後任ということでしたが、前任の先生も、前々任の先生もかなりタカ派の論客でしたので、わたしで務まるかと不安でしたが、案の定のことが起こりました。参加者は20名ほど(大半がわたしより高齢でした)。まず講師が小一時間レクチャーし、残りの一時間は質疑応答という形で行われましたが、発言したのは3名ほど(参加者のなかの古参のリーダーだと思います)。まずわたしが用意した資料のなかに朝日新聞の記事があったことから糾弾が始まりました。「なぜ偏向した朝日を使うのか」というのです。そして「なぜ先生は(前任者のように)はっきりと日本も核を保有すべきだと言ってくれないのか」とか「自分は徴兵制が必要だと考えるがどう思うか」とか、その3名がわたしに詰め寄り、わたしが反論するという形になりました。他の参加者はそのやり取りを黙って拝聴しているというあんばいでした。対話は成り立たないと感じたわたしのほうが根負けし、3回で講師を止めさせていただきました。もう何年も続けられてきた市民講座らしいのですが、結局コアとなる声の大きな人たちが場の空気をつくり、講座内の「世論」を形成してしまうのだろうと思った次第です。
 しかし、たとえ発言はしなくても、核武装に反対の人も多かったのではないですか?
しかし、たとえ発言はしなくても、核武装に反対の人も多かったのではないですか?
そうかもしれませんが、同調圧力が働くことは否めません。もう一つ体験談を述べましょう。わたしは大学で「安全保障論」という講義を受け持っています。半期14回のうち、4回ほどは核兵器の問題を取り上げます。「NHK特集 核戦争後の地球」というやや古い映像資料をDVDにしたものや、冷戦時代に作られた米国映画「THE DAY AFTER」のさわりの部分、サーロー節子さんのノーベル賞授賞式時のスピーチなどを見せたりして平和への意識を喚起する一方で、核兵器の種類や性能、核抑止力の論理、核兵器の国際政治における役割などリアリズムの観点からの考え方も説明します。
わたしは毎回授業のあと、課題を出したりコメントシートに感想を書いてもらったりしていますが(それが成績評価の一部となります)、あるとき、ちょっと学生を「挑発」するような言い方で、「ロシア、中国、北朝鮮という核を持った国に囲まれて、日本は大丈夫なのか」と問題を投げかけてコメントを出させたところ、なんと半数近くが「日本もそろそろ核を持つことを検討すべき」と書いてきたのです。わたしは責任を感じ、翌週の授業で「本当に君たち、それでいいのか」と議論を蒸し返したりもしたのですが、実は学生も、そんなに深く考えているのではありません。教師が平和を唱えれば、大半はそれに同調した解答を書いてきますし、強硬な論を述べれば、またそれに賛同する解答を提出します。教師の論調に合わせて解答すれば無難だ、下手に異なった意見を書いて単位を落とされては困るという心理が働くのです。わたしが学生の時も同じようなものでしたから(チェーホフをべた褒めすれば絶対単位をくれると言われている先生がいて、わたしも大して読んでいないチェーホフを礼賛した答案を書いた記憶があります)、今の若者を難じるつもりは全くありませんが、影響力や人気のある政治リーダーの出現で、一気に物事は動きかねません。核保有の問題も例外とは思われません。
—————————————
