 中谷防衛大臣は7月15日午前の閣議で、2025年版の防衛白書を報告し、了承されました。その中身は防衛省・自衛隊のウェブサイトでも公開されています。
中谷防衛大臣は7月15日午前の閣議で、2025年版の防衛白書を報告し、了承されました。その中身は防衛省・自衛隊のウェブサイトでも公開されています。
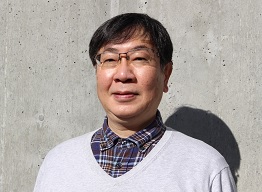 白書ではわが国周辺における中国軍機や空母の活動の活発化、北朝鮮による極超音速兵器の開発、中国軍とロシア軍の連携強化や覇権主義的な動き等々に強い懸念を表明し、「国際社会は戦後最大の試練の時を迎え、新たな危機の時代に突入しつつある」との見方を示しました。
白書ではわが国周辺における中国軍機や空母の活動の活発化、北朝鮮による極超音速兵器の開発、中国軍とロシア軍の連携強化や覇権主義的な動き等々に強い懸念を表明し、「国際社会は戦後最大の試練の時を迎え、新たな危機の時代に突入しつつある」との見方を示しました。
特に中国軍への警戒を前面に打ち出し、台湾問題に関しては、軍と海警局が連携し、武力攻撃に至らない形での現状変更をめざす「グレーゾーン事態」の作戦能力の向上を図っていると警告しています。こうした防衛白書の記述に対して、中国外務省高官は「強烈な不満と断固たる反対」を表明し、日本政府に抗議したことを明らかにしました(『京都新聞』7月16日)。日本周辺もきな臭さが増した感が否めませんがいかがでしょう?
いよいよ「台湾有事」が仮定の話ではなく、現実味を帯びてきたように思います。つまり、それが起こるか起こらないかではなく、いつ起こるかという問題へとシフトしてきているように感じるのです。昨年、台湾では中国の台湾攻撃を題材としたドラマ「零日攻撃 ZERO DAY ATTACK」が製作され、今年8月2日からテレビ放映されるそうです。これも危機感の表われでしょう。日本でも8月15日からアマゾンプライムビデオで配信されるとのことですので、わたしもしっかり見てみようと思っています。
また、台湾では7月9日から18日まで「漢光」と呼ばれる軍事演習が行われました。これは毎年1回行われているものですが、中国の軍事圧力の高まりを受け、今年は過去最長の10日間の演習となったそうです。これには一般市民も参加し、台南市など3都市で避難訓練も行われました(『讀賣新聞』7月11日)。
 避難訓練といえば、今年5月、沖縄県の浦添市でも弾道ミサイルの飛来を想定した避難訓練が行われましたね。沖縄では与那国町や那覇市などの訓練に続き4例目とか。どの国からのミサイルかは明示されていませんが、これも台湾有事が念頭にあることは明らかでしょう。
避難訓練といえば、今年5月、沖縄県の浦添市でも弾道ミサイルの飛来を想定した避難訓練が行われましたね。沖縄では与那国町や那覇市などの訓練に続き4例目とか。どの国からのミサイルかは明示されていませんが、これも台湾有事が念頭にあることは明らかでしょう。
こうして戦争になれば住民が最大の犠牲者になることは台湾も沖縄も一緒です。そう考えると、台湾と沖縄はとても似ていると感じるのですが、いかがでしょう?
そのとおりです。どちらも本土との統一という問題で翻弄されてきました。ただ、「統一問題」に限っていえば、両者には大きな違いがあります。第二次世界大戦後の沖縄は、「本土復帰」をいわば県民の総意として強く望み、幾多の困難や県民の闘争を経て、1972年5月15日に悲願を達成したのです。もし台湾の人々も、沖縄の場合と同じように本土統一を念願しているのであれば、中国本土はそれを叶えるべく尽力すべきです。しかし、台湾の世論が統一を望んでいないのであれば、それをすべきではありません。大半が望んでいないことを力づくで実行することは、強者による弱者への暴行にほかなりません。いくら習近平政権が台湾統一を民族の悲願だと言い繕っても、台湾が望んでいない統一を行う道理はありません。中国側はこれを内政問題だと言いますが、弱者を力で蹂躙することに国際社会が「ノー」と言うのは当然の義務です。
 では、中国による台湾進攻を日米が中心になって阻止することも義務なのですか?
では、中国による台湾進攻を日米が中心になって阻止することも義務なのですか?
そこで問題がすり替えられてしまうように思うのです。軍事力による統一を、軍事力によって阻止する行為は、結局のところ当事者である台湾と、日米両部隊の出撃基地となる沖縄の破壊をもたらします。つまり一番の被害者は台湾と沖縄の住民です。それぞれ「統一」「統一阻止」という名のもとに、いくら正義を唱えたところで、住民を犠牲にした戦いを行えば、どちらも同罪です。流行りの言葉を使えば、統一問題は弱者である「台湾ファースト」「沖縄ファースト」で考えなくてはならず、それをサポートするのが文民である政治家たちです。政治家はあくまでも軍事ではなく政治的な手法で解決策を見出さなくてはなりません。政治家が政治を手放し、軍事当局者に解決を委ねたら政治家失格なのです。ところが昨今の風潮として(これは国際的な風潮といえるかもしれませんが)、軍事当局者が政治家を軽んじ、前面に出ようとする傾向が看取されるのです。
 それは具体的にはどのようなケースでしょう?
それは具体的にはどのようなケースでしょう?
:台湾問題に即していえば、今年4月に日米の軍当局者は、初めて「台湾有事」を想定し、共同演習「キーン・エッジ24」を実施しました。これに中国の国防部が大反発し、同部の報道官が4月16日、もし日米が「頑なに『台湾カード』を切って中国の内政に干渉し、さらには身の程知らずにも軍事的挑発を行うのであれば、必ずや耐え難い代償を払うことになるだろう」と恫喝的な声明を出しました。
ここに登場するのは日・米・中の軍事当局者であって、まるで彼らに台湾の運命を決める力があるかのようです。いったい政治家はどこに隠れてしまったのか。わたしは文民統制(シビリアンコントロール)の原則が侵食されていくことを今いちばん恐れています。軍部が政治家を差し置いて、事態の打開を図ろうとするとき戦争が始まるからです。
—————————————
河原地英武<京都産業大学国際関係学部教授>
東京外国語大学ロシア語学科卒。 同大学院修士課程修了。 専門分野はロシア政治、安全保障問題、国際関係論。 俳人協会会員でもある。 俳句誌「伊吹嶺」主宰。
