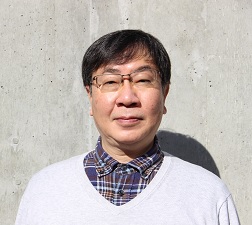
 ウクライナ戦争が始まってから3年数カ月、ガザ紛争の開始から1年9カ月、そして先月にはイスラエル・米国によるイラン攻撃とイランの反撃があり、世界がだんだん戦争や軍事紛争によって蝕まれているような印象を受けますが、アジアは大丈夫なのだろうかと不安になります。特に数年前から「台湾有事2027年説」が取り沙汰されるようになりました。
ウクライナ戦争が始まってから3年数カ月、ガザ紛争の開始から1年9カ月、そして先月にはイスラエル・米国によるイラン攻撃とイランの反撃があり、世界がだんだん戦争や軍事紛争によって蝕まれているような印象を受けますが、アジアは大丈夫なのだろうかと不安になります。特に数年前から「台湾有事2027年説」が取り沙汰されるようになりました。
その2027年まであと1年半となりましたが、その可能性は一体どうなのでしょう?
2027年を台湾危機の年とする根拠はいくつかあるようです。第一に中国の海軍力が米国のそれを圧倒するのがその時期で、かりに米国と軍事対決した場合、中国が勝利を確信できるのは2027年頃という説。
第二に2027年は中国人民解放軍創設100周年にあたり、習近平政権としても解放軍による「国家統一」という実績を示したいとの思惑があるのではないかとする説。
第三に習近平総書記(国家主席)は2022年の中国共産党大会で異例の3期連続が承認されましたが、その任期が終わるのが2027年です。そこで幕引きとなるのか、それとも続投を図るのかは未知数ですが、かりに台湾統一が達成されれば、彼の大きな功績とされ、続投機運も高まるというものです。
そして第四に、2028年前半には台湾の総統選挙がありますが、再選を目指す頼清徳総統は中国に対し強硬な姿勢を打ち出し、それを口実に中国が2027年台湾統一に乗り出すという説もあります。台湾当局も今年3月、中国による軍事侵攻のあり得る年として初めて2027年を明示し、大規模軍事演習の実施を決めました。
中国軍も年内にロシア国内でロシア軍から軍事訓練を受け、ウクライナ侵攻で得たノウハウを学ぶ計画があるらしいとの情報もあります。この情報がどの程度確かか不明ですし、それが台湾有事とどう関係するのかもよくわかりませんが不気味ではあります。
 そのような説を聞いていると、なんだか2027年が避けがたい宿命的な年のような気にさせられますが、実際には台湾市民も中国国民も、そして米国や日本の国民にしても、戦争など望んでいるはずがありません。世論が支持しないのになぜ台湾有事が起こるなどと想定するのでしょうか?
そのような説を聞いていると、なんだか2027年が避けがたい宿命的な年のような気にさせられますが、実際には台湾市民も中国国民も、そして米国や日本の国民にしても、戦争など望んでいるはずがありません。世論が支持しないのになぜ台湾有事が起こるなどと想定するのでしょうか?
国際政治の研究に携わっていると、国民一人一人が戦争を嫌う気持ちをもっていることは戦争を止めるブレーキになり難いという感を抱かざるを得ません。
ユネスコ憲章の前文は「戦争は人の心の中で生れるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築かなければならない」という崇高な一文で始まっています。
わたしも確か高校の英語の教科書で読んだ記憶があり、以来、心に深く刻まれた言葉となっています。しかし年を重ねるにつれ、「人の心」という抽象的な言葉ではひ弱すぎるのではないかと感じるようになっています。本当に戦争を防ぐにはもっと具体的、物理的な保証が必要です。その点で、やはり日本国憲法の第九条は格段の具体性があります。一切の戦力を放棄すれば戦争を起こしたくても起こすすべがありませんから。今日の日本の防衛装備をみれば、九条は死文化しているとも言えますが、それでもこの条文があるかぎり、わが国が公然と戦争をすることはできませんのでブレーキとしての機能はまだまだ果たしています。これが取り払われたとき、わが国でも「自存自衛」という名の戦争の敷居が一気に低まるのだろうと思います。国民もいやいやながら、徐々に戦時体制に向けて気持ちが慣らされていくのです。
 気持ちが慣らされるとは?
気持ちが慣らされるとは?
いつの間にか日本のマスコミもウクライナ戦争やガザ地区の惨状をあまり大きく取り上げなくなりました。国民が慣れっこになってしまい、ニュースバリューが落ちたからです。米国のイラン攻撃も一過性のこととして過ぎ去った感があります。
為政者は戦争を戦争という名では行いません。そして戦争とは政治の一手段だと考え、コントロールできると過信するのです。米国のトランプ大統領も、イランを核放棄のための交渉のテーブルに着かせるために、手荒な方法を使ったまでだという感覚でバンカーバスターを投下させたのでしょう。
しかし戦争はいったん始めてしまうと、政治家の手には負えなくなることは歴史が示しています。ウクライナ戦争にしても、ロシアのプーチン政権は「特別軍事作戦」として開始し、泥沼化させてしまいました。日本もかつて日中戦争の深みへはまっていく端緒は1937年7月7日の盧溝橋事件でした(88年前の昨日)。当時の日本政府は「不拡大」の方針でしたが、結局はとてつもない戦争になってしまったことは周知の通りです。
 戦争の発端は、ローカルでささいな軍事的いざこざの場合が多いということでしょうか?
戦争の発端は、ローカルでささいな軍事的いざこざの場合が多いということでしょうか?
はい。当初は軍当局者間の衝突であって、政治家もすぐに鎮静化できると考えてしまいがちですが、いつの間にか軍部に引っ張られ、どんどん戦争へと深入りしていく構図は歴史の中でしばしば見られることです。軍にもプライドがありますから、やられっぱなしでは終われません。一矢報いてから矛を収めようとするうちにエスカレートします。ひとたび戦争の歯車が回りだすと、もはや政治家も国民も止められず、行きつくところまでいかざるを得ないという事態になりかねません。ですから「最初の銃声」を轟かせないことが肝心です。しかし昨今の東アジア情勢は、軍当局者による挑発行為が目につくようになり心配です。
 たとえばどのような事態ですか?
たとえばどのような事態ですか?
最近のニュースですと、6月7日と8日、中国軍の戦闘機が西大西洋の公海上で2度にわたって海上自衛隊の哨戒機に異常接近するという事件がありました(『朝日新聞』6月17日)。また、海上自衛隊の護衛艦「たかなみ」が6月12日、台湾海峡を通過していたことが政府関係筋によって明らかにされました。同月14日に実施されたフィリピン海軍との共同訓練に向かう途中、軍事活動を活発化させる中国を牽制する目的で、あえて台湾海峡を通過したとのことです(『朝日新聞』6月20日)。また、日本政府は6月27日、外国軍の無人機が領空侵犯した場合、自衛隊は正当防衛や緊急避難に当たらなくても撃墜できるとの見解を閣議決定しました。
かりに撃墜した場合、先方が報復攻撃する可能性もあり、それがより大きな軍事紛争にエスカレートするのでないかと危ぶまれます。アジア地域も欧州や中東に続いて戦場にならないという保証はありません。アジアも戦争に向けての条件が整いつつあるように見えますが、この状況にわれわれ国民が慣れてしまうことを何より恐れます。
—————————————
河原地英武<京都産業大学国際関係学部教授>
東京外国語大学ロシア語学科卒。 同大学院修士課程修了。 専門分野はロシア政治、安全保障問題、国際関係論。 俳人協会会員でもある。 俳句誌「伊吹嶺」主宰。
