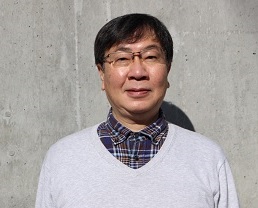
 今回の「国際講座」はけっこう刺激的なタイトルですが、「戦争中毒」とはどういうことなのですか?
今回の「国際講座」はけっこう刺激的なタイトルですが、「戦争中毒」とはどういうことなのですか?
一般にわれわれは健康によくないことを続けているうちに、それが悪癖となってやめられなくなります。たばこの場合ならニコチン中毒、お酒であればアルコール中毒、薬物であれば麻薬中毒、そして射幸心をあおるパチンコ等の遊戯から賭博までをひっくるめたギャンブル依存症なども一種の中毒でしょう。
中毒症状の特徴は、最初のうちは自分がきちんとコントロールできていると過信することです。やめようと思えばいつでもやめられると考えているうちに、どんどん深入りして取り返しがつかないことになります。昨今の国際政治を見ていると、それとよく似た現象が生じていることに気づきます。
 たとえばどのような現象でしょう?
たとえばどのような現象でしょう?
おそらく誰もが気づいているのは米国のトランプ大統領の変質です。トランプ氏は本来「ディール(商取引)」の人であって、大統領就任以前からウクライナやガザの戦争でも「無益な血を流すな」「ただちに戦いを止めよ」という立場をとってきました。ところが米ロサンゼルスでの非正規移民摘発への抗議デモに対して州兵や海兵隊の出動を命じたり、米陸軍創立250年を祝う軍事パレードを行ったり(それも自分の誕生日と同じ日に)と、軍事依存への傾斜を強めています。
極めつけは、イランへの軍事攻撃でした。トランプ大統領はイスラエルによるイラン空爆の「成功」を祝福し、イランに無条件降伏を迫るとともに、6月19日にはイランが外交的解決に復帰するための猶予として2週間という期限を設定しました。ところが3日後の6月22日、B2ステルス爆撃機でイランの核施設にバンカーバスター爆弾を投下させたのです。米当局がこれを「ミッドナイトハンマー(真夜中の鉄槌)」作戦と呼び自画自賛したことは周知のとおりです。これは交戦国ではない主権国家への先制攻撃であって国際法違反ですし、核施設への攻撃も国際法に照らして違法です。今まで民主主義陣営は「法の支配」「法による秩序」を盾として専制主義体制に対抗してきました。しかし米国自らがそれをかなぐり捨て、専制主義国家と同じ行動に走ってしまったわけです。
 ですがトランプ大統領はすぐにイランとの交渉再開を宣言しています。あくでも外交的解決を目指しているのではないのですか?
ですがトランプ大統領はすぐにイランとの交渉再開を宣言しています。あくでも外交的解決を目指しているのではないのですか?
そこが問題なのです。トランプ大統領は軍事力の行使を政治の一手段と考え、自分はすぐにまた政治に復帰できると考えています。つまり戦争は自由にコントロールできると過信しているのだと思います。まさに「戦争中毒」の始まりです。爆撃という劇薬を使ってイランを屈服させたトランプ氏は、今後交渉が進捗しなければ、また同じ「劇薬」の使用に踏み切るのでしょう。こうして戦争の誘惑に取り込まれていくのです。実はロシアのプーチン大統領も、ウクライナのゼレンスキー大統領も、イスラエルのネタニヤフ首相も、そしてイランのハメネイ師も、みな同じ罠にはまってしまったのだと感じます。
 それはどういうことでしょう?
それはどういうことでしょう?
それぞれの政治指導者は、いつでも自分は戦争を止める用意があると述べ、現に止めようと思えば止められると考えています。ただし、相手が止めないから自分も止めないだけだと自己正当化するのです。しかし、いつでも止められると言いながら、ずるずると深入りしていくのが中毒の典型的な症状です。そして中毒には、後戻りできなくなるような「蜜の味」があります。だからこそ中毒なのです。
 「蜜の味」とは端的に言うと何ですか?
「蜜の味」とは端的に言うと何ですか?
戦争が止められなくなる経済的な利益です。米国防省は今回、さかんにB2ステルス爆撃機(1機約3000億円とも)やバンカーバスター爆弾の映像をメディアに流しました。その目的は2つでしょう。国内的には、その威力をトランプ大統領に分からせ、軍事予算の増額へ結びつけること、対外的には、米国製の兵器を世界に売り込むことです。実際、英政府は6月24日、(このステルス機ではありませんが)核搭載可能な最新鋭の米国製ステルス戦闘機F35Aを12機購入する計画を発表しました(『京都新聞』6月26日)。
 そういえば、NATOも防衛費をGDP比5%に増額することに決めましたね。
そういえば、NATOも防衛費をGDP比5%に増額することに決めましたね。
はい。6月25日、オランダ・ハーグで開かれていたNATO首脳会議は、加盟各国が防衛費をGDP比5%に引き上げることで合意しました。米国の強い要求に応じた形です。不気味なのは、米国が同じことをアジアの同盟諸国にも迫っていることです。
増額された防衛予算で米国製の兵器を導入せよという意図もあるのでしょうが、それにしても5%とは常軌を逸しています。もはやこれは抑止のためというより、戦闘準備段階に入ることを意味する金額でしょう。防衛予算が膨らめば、必然的に軍当局者の威信は高まります。外交より軍の存在感が増すのは必定です。
国際法を軽視し、戦争の敷居をどんどん下げていく政治家たち(トランプ氏もその列に加わりました)、膨大な予算を獲得し、威信を益々高めていく軍部、そこから多くの利益を引き出す軍需産業、これらが三位一体となって世界を戦争への引き込んでゆく構図が目に浮かびます。世界中が「戦争中毒」へとのめり込んでいくのを、われわれは目の当たりにしているのだといえば杞憂でしょうか。
—————————————
河原地英武<京都産業大学国際関係学部教授>
東京外国語大学ロシア語学科卒。 同大学院修士課程修了。 専門分野はロシア政治、安全保障問題、国際関係論。 俳人協会会員でもある。 俳句誌「伊吹嶺」主宰。
